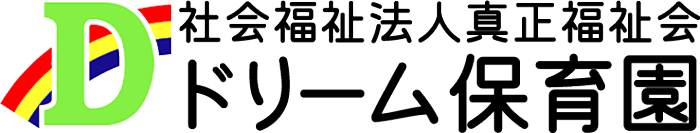ドリーム保育園の職員・保護者の皆様、そして当法人の理事役員の皆様初め、関係各位へ向けて発信するこの「ドリームかりゆし便」を、今年度より非定期でお届けしたいと思っています。
私が個人的に購読している情報紙から、特に重要だと思う記事に関して、皆様にもわかりやすく要約してお伝えし、心と身体の健康管理に活かせていただけたらこの上なく幸甚です。
さて、第1回目に取り上げたいことは、『「頭がスッキリ 動きはキビキビ 脳を守る」世界標準の認知症予防法』というテーマで、~国際学術誌も認めた「4つのプログラム」の圧倒的な効果~ の副題で、神戸大学大学院教授の古和(こわ)久(ひさ)朋(とも)氏が、文芸春秋2025年4月号 270ページに掲載した記事を紹介します。
14ページにも及ぶ膨大な情報ですので、原版を読んでもらったほうが良いのはいうまでもありませんが、私自身の理解度が深まること、そしてドリーム保育園の保護者の親世代の方々や法人の理事役員など、関係各位へも広くお伝えしたいとの想いで、3枚程度にまとめてみようと考えました。保護者の親世代というと、相当な幅はあるでしょうが、50代から70代といったところだと思いますが、今年66歳になる園長も、8年前の冬、「脳幹出血」という病に襲われ、健康長寿の大切さを痛感する者として、同じ状況の方や、必要な知識を得ることでこのような病から守られることができれば、との思いから記事をまとめてみたいと思います。
【前書き】
認知症という誰もが発症する可能性がある病は、新薬も開発されてはいますが、現在の医療では治すことはできません。レカネマブやドナネマブなどの新薬は、進行を遅らせるためのもので、発症前に戻すことはできず、投与は脳の浮腫や脳出血のリスクがあり価格も高く軽症認知症の患者さんに対して慎重に投与することでメリットがあります。
しかし、認知症にならないように、発症リスクを下げる“予防”は可能であると明らかになりました。筆者の研究グループが、認知症の発症リスクがある高齢者を対象に“運動”を主体としたプログラムを継続することで認知機能が改善されたと、世界アルツハイマー協会の国際学術誌にその成果が掲載されました。たとえ80代でも予防を始めるのには遅くはないということです。
【①1年半後にはキビキビ 兵庫県丹波市での研究】
高齢者の認知症は増えており、日本では2022年、443万人が高齢者の認知症といわれ、3.6人に1人が認知症若しくは予備軍。世界でも2019年、5700万人が認知症といわれ、2050年には1億5300万人に達すると予測されています。
こうした中、医学誌「ランセット」は認知症発症のリスク因子14項目をとり挙げています。
①教育不足。②高血圧、③聴覚障害、④喫煙、⑤肥満、⑥抑うつ、⑦運動不足、⑧糖尿病、⑨社会的孤立、➉過剰飲酒、⑪頭部外傷、⑫大気汚染、⑬視力低下、⑭LDL(悪玉)コレステロール値の上昇。これらのリスク因子を取り除くことで、認知症になる人の45%が予防できるとしています。また、生活習慣を改善することで、認知症の予防につながります。 兵庫県丹波市は以前から保健師を中心に高齢者の健康増進に取り組んでいた自治体ですが、2019年7月に、2つの病院を統合し「兵庫県丹波医療センター」という総合病院になり、筆者の研究グループも丹波市の取り組みに合わせて「PRAIME
TAMBA」と銘打った研究を立ち上げました。
この研究では、65歳から85歳の、血圧や血糖値が高く動脈硬化のリスクがあり物忘れの自覚がある203人の高齢者が研究対象で、2つのグループ、ひとつは「①運動、②認知機能トレーニング、③栄養管理、④生活管理の4項目からなるプログラムを行うグループ(介入群)。もうひとつは、健康に関するパンフレットのみ渡し、プログラムは実施しないグループ(待機群)に分け、1年半の期間認知機能や身体機能の検査を行なった結果、認知機能は両群とも向上してはいましたが、介入群が待機群より上がり幅が41%大きく、明らかな差異が見られました。
【②体と脳を動かす「二重課題運動】
介入群の4つの項目についてみてみると、まず①運動ですが、参加者は週1回体育館に集まり理学療法士の指導でストレッチや筋力・持久力運動の他二重課題運動にも取り組んでもらいました。この二重課題運動とは、「ながら運動」とも言え、じんわりと汗をかく程度の運動をしながら数字の計算などの認知課題を組み合わせた運動で、かなりの成果を上げ、この二重課題運動は諸外国へも紹介され効果があったそうです。これを読んでいる皆さんが二重課題運動を実践してみるなら、ウォーキングしながら簡単な計算やしりとり、川柳を作るといったことなどがお勧めです。アメリカのピッツバーグ大学の研究では、ウォーキングなどの有酸素運動によって脳の記憶を司る海馬の容積が2%増加するとのこと。週3回のウォーキングを40~50代で40分以上、60代以上なら20分以上が目安とのことです。更に、これらのトレーニングは、一人で黙々と実施するより、仲間同士で楽しく実施することも、続けるには大事なことです。
【③卵は良い?悪い? 食事で認知症予防】
運動機能、認知症機能の次は、栄養管理です。管理栄養士や保健師が半年に1回の個別面談で栄養指導を行いました。一日三食バランスの良い食事を心掛け、認知機能低下を予防する食品を知ることも大事です。10種類の食品と一日に取り入れる目安を示して毎日7種目以上は食べるように指導しました。その10品目とは、①魚介類(手のひら一つ分)、②肉類(手のひら一つ分)、③卵(一個)、④牛乳(コップ一杯)⑤大豆・大豆製品(手のひら一つ分)、⑥野菜(五皿程度)、⑦海藻類(一日一回)、⑧いも(こぶし一つ分)、⑨果物(こぶし一つ分)、➉油脂(大さじ一杯)。卵に関しては、コレステロールは近年問題視されなくなりましたが、飽和脂肪酸が含まれているため摂りすぎるとLDLコレステロールが増加します。高齢者の卵の摂取には栄養士などには慎重な姿勢の方が多いようですが、筆者は積極的に摂ることを勧めています。また、国立長寿医療研究センター(長寿研)の研究では、緑茶を一日二杯以上飲んでいる人は、ほとんど飲んでいない人に比べ、認知機能が下がりにくいという結果が出たそうです。緑茶に含まれるカテキンはポリフェノールの一種で、アミロイドβという老廃物を排出するのを助ける働きがあることがわかったそうです。更に、カレーに含まれるターメリック(ウコン)は黄色の色素成分のクルクミンというポリフェノールが含まれているため、カレーを月1回一年以上食べると認知機能低下のリスクが下がることも確認されているそうです(ハウス食品・東大共同研究)。また、認知機能に重要な役割を果たすドコサヘキサエン酸が含まれ、血栓を防ぐエイコサペンタエン酸も含まれる青魚も筆者は週三回勧めています。
食事に関しては、一概には言えないとしながらも、一日三食きちんと摂ることを勧めています。空腹の状態が続くことで、血糖値の乱高下を繰り返し血管がダメージを受けて動脈硬化や心筋梗塞のリスクが高まるそうです。
【④モニタリングすべきは「睡眠時間」と「歩数」】
睡眠時間の確保も認知症予防に欠かせない要素です。イギリス人約8千人を50歳から25年間にわたって追跡調査した研究では、睡眠時間が6時間以下の人は7時間以上に比べて、認知症発症リスクが30%高くなっていたそうです。長寿研の研究でも、就寝時間が午後11時以降の高齢者は、午後9~11時の人と比べて認知症リスクが2倍近くも高かったという結果が報告されています。日中に排出しきれなかったアミロイドβは、寝ている間に排出されるそうですが、睡眠不足が続くと脳内のゴミを掃除する機会が無くなることになるのです。
週3回以上の運動習慣を持っている高齢者は認知症になるリスクが低く、60代以上で20分以上のウオーキングで効果があるという研究があります。認知症の7割を占めるアルツハイマー症の場合、70代での発症が最も多くなりますが、既に50代前後から認知症の潜伏期間に入る人もいます。50代前後はちょうど食生活の乱れや運動不足、喫煙や過度の飲酒によって脳梗塞や糖尿病といった生活習慣病になりやすい世代にあたり、食生活を見直し、運動や睡眠の改善なども積極的に取り組んでいけば、20年後は元気な70代を迎えられると思います。
「かりゆし便 #1」は、私たち誰でも罹る可能性のある「認知症」について、予防法などを紹介しました。次回の発行時期やテーマはまだ未定ですが、心と身体の健康に良いと思われる情報をご紹介しますので、ぜひお楽しみに!